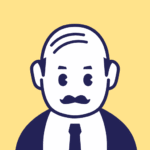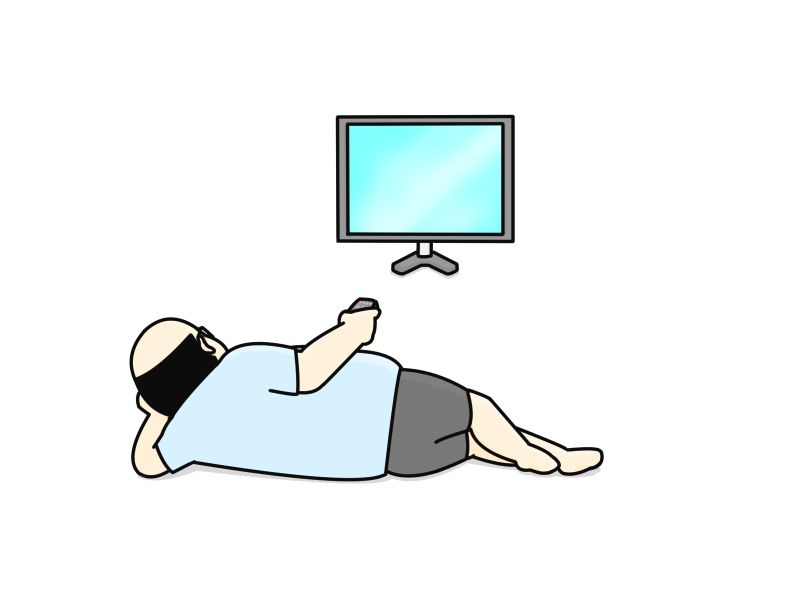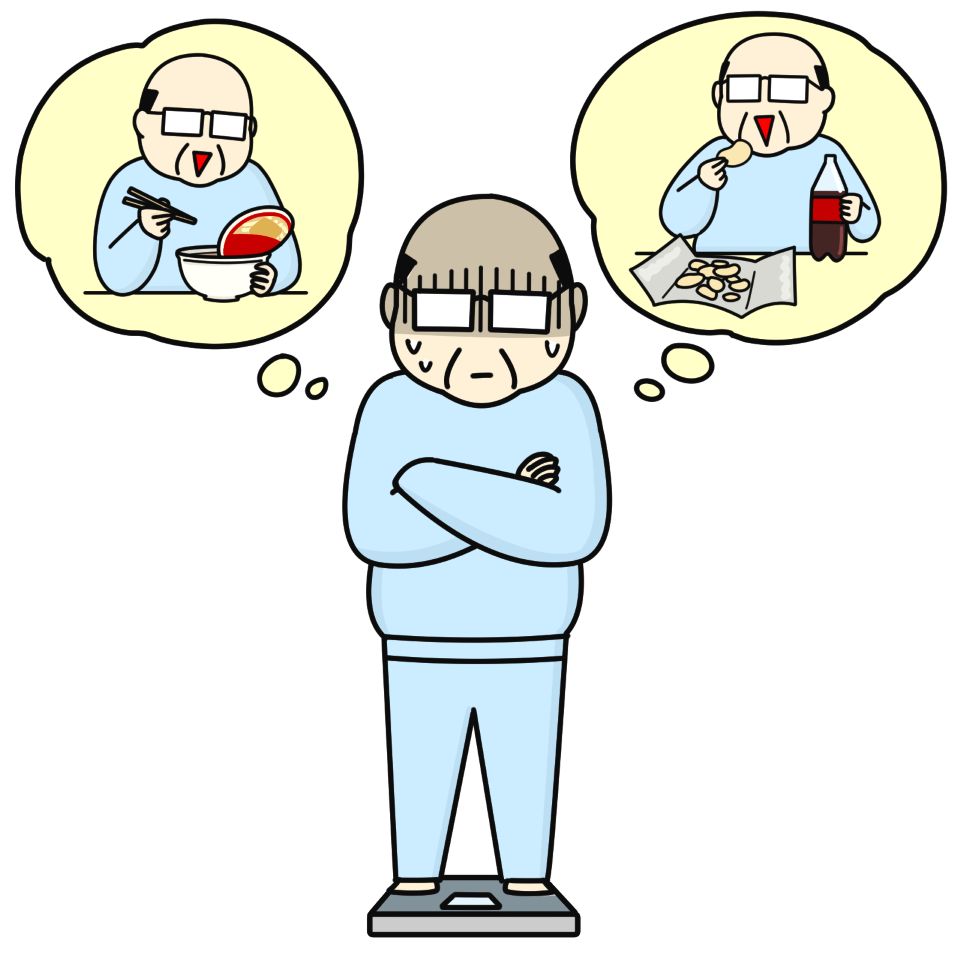【おじさん必見】知ってた?「ひやむぎ」と「そうめん」の決定的な違い
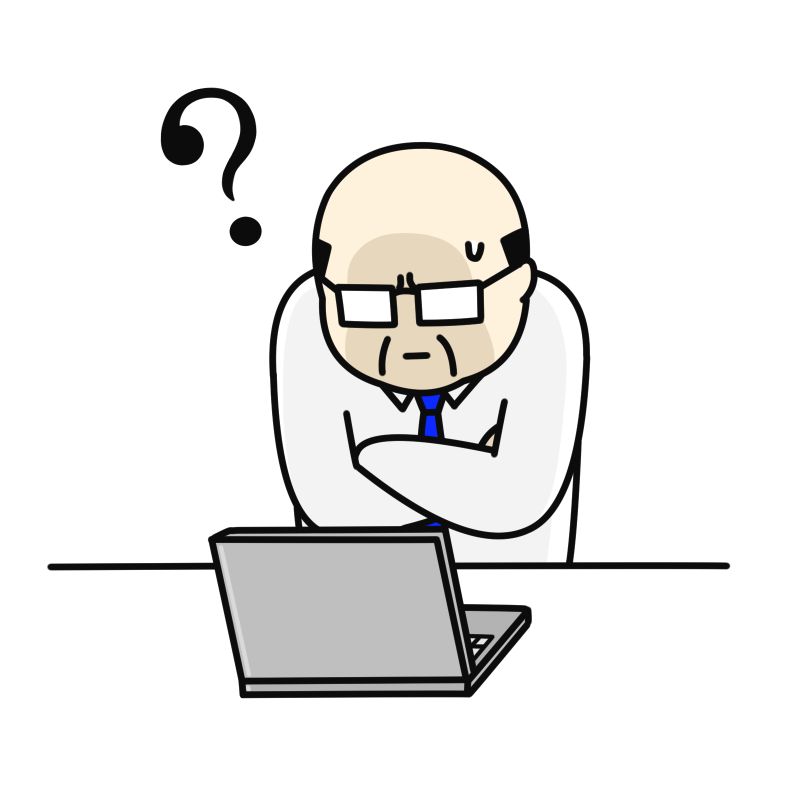
「おじさんのためのひやむぎとそうめん講座」と題して、今日はこの2つの麺の秘密に迫ります。
「え、ひやむぎとそうめんって同じものだったの?」と驚いたあなた。安心してください、私もそうでした。
子供の頃、お袋が「今日はひやむぎよ!」と言いながら出してくれた麺に、心の中で「これ、そうめんと何が違うんだ?」とずっと疑問に思っていました。
結論から言えば、そうめんとひやむぎの最大の違いは「太さ」です。
日本の伝統的な製法である「手延べ」で作られる場合、麺の太さがだいたい直径1.3mm未満のものが「そうめん」、直径1.3mm以上1.7mm未満のものが「ひやむぎ」とされています。
このルール、実は日本農林規格(JAS)で厳密に定められています。
なんだか、お役所の書類みたいで面白くない話ですが、このルールを知っておくと、ちょっとしたウンチクとして使えますよ。

それと、1.7mm以上のものは「うどん」だね。
麺の世界も、なかなか奥が深い。
太さだけじゃない!「そうめん」と「ひやむぎ」の歴史と伝統
「手延べ」という言葉が出てきましたが、この製法こそが、そうめんやひやむぎの美味しさの秘密です。
手延べそうめんは、奈良時代に中国から伝わった「索餅(さくべい)」がルーツとされています。
小麦粉と米粉を練って縄のようにねじったもので、お菓子や保存食として食べられていたようです。
それが時代とともに変化し、室町時代には現在のような細い麺になったと言われています。
一方、ひやむぎは、うどんを冷やして食べるようになったことが始まりと言われています。
室町時代に、熱いうどんを水で冷やして食べるのが流行し、それが「冷や麦」と呼ばれるようになりました。

昔は、熱いうどんを「あつむぎ」、冷たいうどんを「ひやむぎ」と呼んでいたって。

ほほう、さっそく知り合いに教えてあげよう。
どっちを選ぶ?「ひやむぎ」と「そうめん」の食べ比べ
さて、太さの違いが分かったところで、実際に食べ比べてみましょう。
そうめんは、細くてのどごしが良いのが特徴です。つるっとした食感と、繊細な香りが楽しめます。冷たいつゆにつけて食べるのが一般的ですが、温かいにゅうめんにしても美味しいです。
薬味は、定番のネギ、しょうが、みょうが、大葉に加えて、ツナ缶やトマトをトッピングすると、おしゃれなカフェ風に早変わりします。
一方、ひやむぎは、そうめんよりも少し太いので、食べ応えがあります。しっかりとしたコシがあり、小麦の風味をより強く感じられます。

きゅうりや錦糸卵、ハムなどを乗せて、冷やし中華風にアレンジするのもおすすめ。
おじさんのための豆知識クイズ!
さて、ここで問題です。
そうめんやひやむぎに、赤い麺や緑の麺が混ざっていることがありますよね。あれ、どうしてだと思いますか?
正解は、「目印」です。
昔は、ひやむぎとそうめんを同じ箱に入れて売っていたそうです。その時、どちらがひやむぎか分かるように、目印として色を付けた麺を混ぜていたのです。
最近では、そうめんやひやむぎを色付きにすることが少なくなりましたが、昔ながらの製法で作られた商品には、今でも赤い麺や緑の麺が入っています。
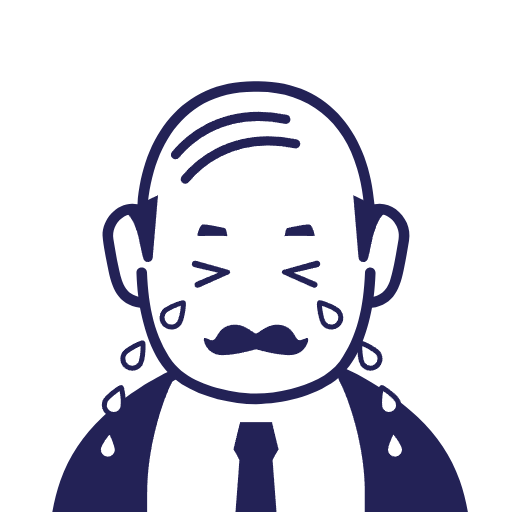
「あの赤い麺、ラッキー麺だったんだな」と思っていたけど、
そうではないのか。とほほ。。。
夏の食卓を彩る「ひやむぎ」と「そうめん」の楽しみ方
さて、ひやむぎとそうめんの違いについて、少しは分かっていただけましたか?
「太さ」と「歴史」を知ることで、いつもの食卓がちょっとだけ豊かになります。
今年の夏は、ぜひ、ひやむぎとそうめんを食べ比べてみてください。
そして、家族や友人に「このひやむぎ、JAS規格では1.3mm以上1.7mm未満なんだぜ」と得意げに語ってみてください。
きっと、「お父さん、また変なこと言ってる…」と白い目で見られることでしょう。
でも、それで良いのです。それが、おじさんの味なのです。
最後に、ひやむぎやそうめんを美味しく食べるためのちょっとしたコツをお伝えします。
- たっぷりのお湯でゆでる 麺がくっつかないように、大きめの鍋でたっぷりの熱湯でゆでましょう。
- ゆで時間を確認する 袋に記載されているゆで時間を守りましょう。
- 冷水でしっかりしめる ゆで上がった麺は、冷水でしっかりしめると、コシが出て美味しくなります。

まだまだ暑い季節、ひやむぎとそうめんを上手に使い分けて、夏を乗り切ろう。

よーし、明日からひやむぎとそうめんの日替わりLifeダゼ☆